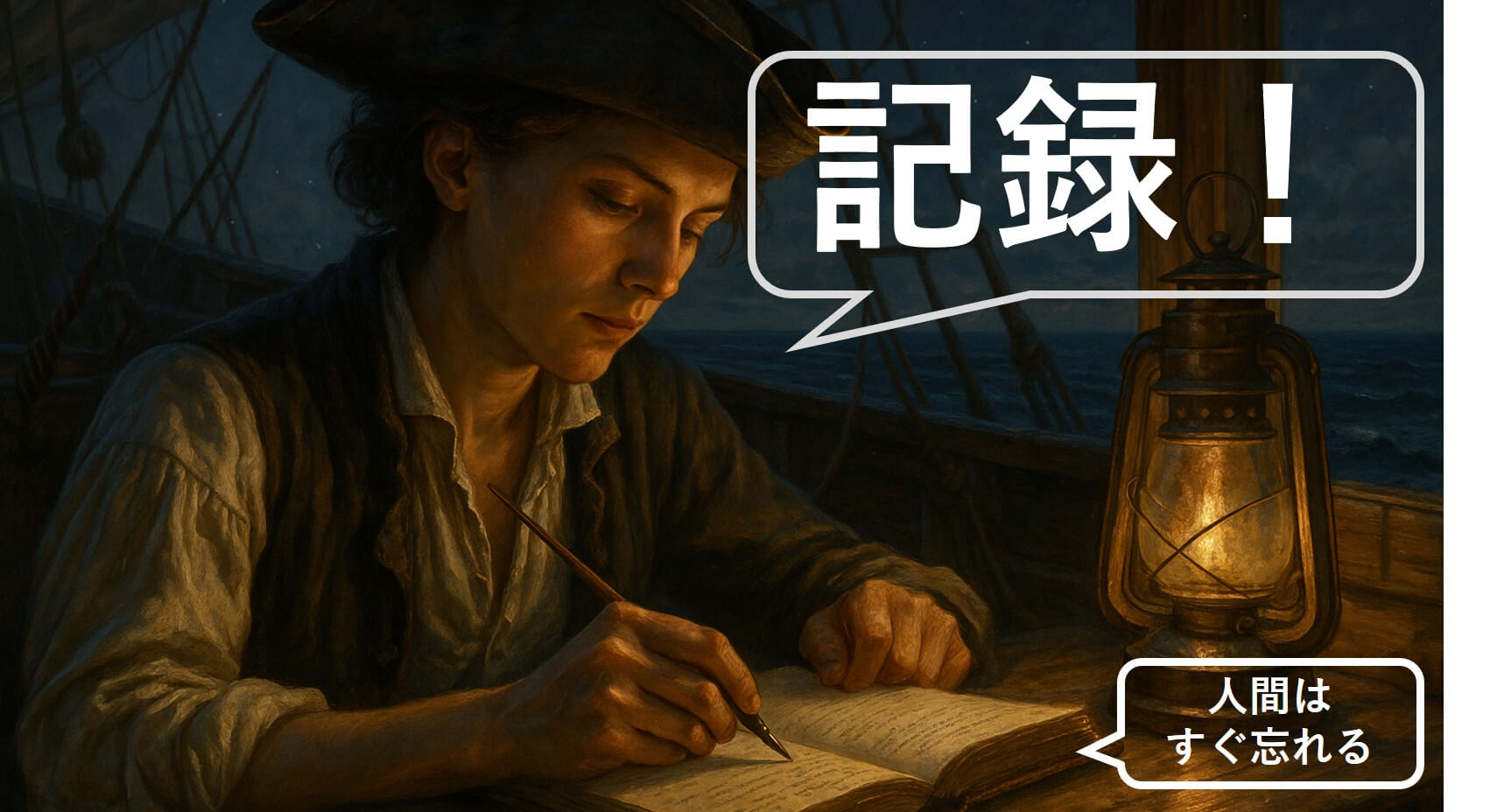ブラック研究室を避けて、ホワイトラボを見つけていく方法

課程博士で必要な査読付き英語論文は1編?2編?
大学を卒業するには、単位を取得して、卒業論文と発表をすればいい。そうすれば、学士の学位は取れる。
修士も似たような感じ?
あれ、博士はさらに難しいの?
と思うかもしれません。
実は博士の学位取得のために必要な項目って、あんまり知られていません。かくいう私も、学部生の時は博士に必要な項目を具体的には全く知りませんでした。
しかし、この無知は、ブラック研究室を避けるために致命的になります。ブラック研究室で最も危険なのは、学位が取れないことです。
ブラック研究室の巧妙な手口
何のこと?と思うかもしれませんが、ブラック研究室では学生が所属する専攻の博士取得ルールをねじ曲げている場合があるのです。
具体的には、査読済み英文論文が1編あればいいのに、ブラック研究室では3編必要である、ということです。もしくは、1編であればいいのは変わらないのですが、三大誌と言われる最高峰の論文しか認めない、という研究室です。
そんなバカなことが?と思われるかもしれませんが、現実にそういうブラック研究室があるのです。そして、そういうブラック研究室ほど、端から見たらビッグラボであったり、研究費が潤沢にあったり、世界的な権威のあるラボである場合があるのです。
なので、博士号取得のための「専攻の基準」と「ラボの基準」を見比べる時に、そもそも「専攻の基準」を把握していることが大事なのです。
今回の記事では、あまり注目されない博士号のルールについて具体例を挙げて詳しく比べてみたいと思います。
博士号取得の3つの方法
理系博士号の取り方は大きく分けて3通りあります。
- ・ 博士課程に行って、課程博士を取る
- ・ 論文博士を取る
- ・ 大きな業績を上げて名誉博士をもらう
最も一般的な理系博士号の取得方法は、博士課程に入学して課程博士になることです。
課程博士は文字通り、3~4年の一定期間、博士号を取得するための課程に在籍し、必要単位を取得することです。ここまで聞くと、修士号と同じと思われるかもしれませんが、博士号取得のためにはここにさらに査読論文の有無が入ってきます。
この査読論文の本数が、学位取得で最も大変な項目になります。
ですが、査読論文の本数は大学院や専攻によってまちまちです。この下にいくつかの大学の博士号取得要項を掲載します。ホームページ上に課程博士の学位申請の情報を見やすい場所に掲載している大学を中心にしています。
重要な注意事項
ここに挙げるのは2025年8月現在であり、あなたの博士号取得時の取得要項と合致している保証はありません。あくまでも参考で見てください。また、取得要項はあくまでも基準であり、実際に入学してみるとさらに厳しい、もしくはさらに優しい場合があります。
なので、博士号取得で悩んでいる方は必ず、志望している研究室の主宰者および事務に問い合わせて確認してください。
自分自身で調べずにいて、いざ博士号を取得しようとして事務に問い合わせると、単位、論文数、在籍年数が足りず、卒業・取得ができないケースはびっくりするほどたくさんあります(本当に、よくある話です)。あくまで、参考資料として自己責任で読んでください。
各大学の博士号取得要項(2025年8月現在)
北海道大学大学院 医学研究科
引用元: https://www.med.hokudai.ac.jp/graduate/yoshiki/index.html
令和8年3月医学院博士課程修了見込者用
医学院博士課程 平成31年度以降入学者対象
学位論文提出等マニュアル
医学院博士課程学位論文募集要項
平成29年4月1日制定
(趣旨)
第3条2 学位論文には,Clarivate Analytics 社 Journal Citation Reports のインパクトファク ターが付与されている,又は同社のインパクトファクターが付与されているものに相当 すると本学院教務委員会資格審査専門委員会(以下「資格審査専門委員会」という。)が 認めた英文学術雑誌(以下「インパクトファクターのある英文学術雑誌等」という。)に 掲載された論文,掲載されることが確約されている論文,又は投稿中の論文であり,学位 授与申請者が第一著者(Equally contributed の場合も第一著者のみ。)となっている論文 (以下「基礎論文」という。)を1編以上添付しなければならない。
東北大学大学院 農学研究科
引用元: https://www.agri.tohoku.ac.jp/jp/education/graduate/#p001
大学院情報 Graduate School Information
学位論文評価基準
博士論文(課程修了によるもの)の評価基準
評価項目
1. 論文の主題の背景にある社会的及び学術的な意義が認められること。
2. 研究内容に新規性、創造性及び食料,健康,環境に関する応用的価値が認められること。
3. 論文の構成及び論述が適切であり、論理展開に整合性が認められること。
4. 独創的な農学研究を企画し、それを先導的に推進する能力が認められること。
5. 専攻分野に関連する先行研究を踏まえた広範な専門知識を網羅し、身につけていることが認められること。
6. 高い倫理性を持って研究に臨んでいたことが認められること。
7. 博士論文の研究内容を公表論文として公表していることが認められていること。
東京大学 大学院理学系研究科・理学部 地球惑星科学専攻・地球惑星物理学科・地球惑星環境学科
引用元: https://www.eps.s.u-tokyo.ac.jp/info/education_thesis/
博士論文の提出要件
課程博士
<2008年度以降博士課程入学者>
地球惑星科学に関連し、申請者を筆頭とする論文が国際誌に1編以上掲載または受理されていることを要件とする。(博士論文と直接関係のない内容の論文でもよい。)
ここでの「国際誌」とは教務委員会で定めたリスト(PDF)に含まれる学術誌を指す。
この要件は博士論文提出時点で満たされていることとする。
博士論文は英語または日本語とするが、前者を強く推奨する。日本語の場合は、英語の長めの要旨と図の説明が必要。
論文は、原著論文、レビュー論文とも可とする。
名古屋大学大学院 医学研究科
引用元: https://www.med.nagoya-u.ac.jp/medical_J/graduate/apply/degree/
学位論文および申請手続について
■学位論文について
・本研究科以外の大学院へ学位論文として提出したことがないもの。
・博士課程入学後、指導教授の指導のもと、実験・研究の上、執筆した論文であること。
・学位を申請する主論文が査読付き英文論文誌にアクセプト済であり、原則として印刷公表された原著論文であること。
(ただし、印刷公表未済のものでも、発表機関の受付証明書又は掲載予定証明書添付であれば可とする。アクセプトメールでも問題ありません。)
・また、学位を申請する主論文については、当該申請者がファーストオーサーでありかつ著者の所属に必ず
名古屋大学大学院医学系研究科の学位申請をする分野の所属であることが明記されていること。
・学位論文は、PubMed収載誌、かつ、Web of Science収載誌のみとなります。
PubMed収載誌とは、MEDLINEに登録されている雑誌を指します。(PMCでの登録雑誌は認められていません。)
Web of Science収載誌とは、SCIEに登録されている雑誌を指します。(ESCIでの登録雑誌は認められていません。)
そのため、指導教員と十分に相談の上、論文を投稿する際には留意してください。
・筆頭著者が複数の場合は「同意書(兼 誓約書)」の提出が必要となります。
京都大学大学院 医学研究科
引用元: https://www.med.kyoto-u.ac.jp/grad_school/mmg/degree_application/
(1)査読者による査定制度を採用している英文学術雑誌(公刊物)に、掲載(受理)され
た原著であること。
(総説論文は、主論文・参考論文ともに不可)
(2)申請時点において、掲載後5年以内のものであること。
(3)本医学研究科博士(後期)課程在学中に、掲載(受理)されたものであること。
ただし、本医学研究科を所定の単位を修得し研究指導認定退学した者で、退学後3年以内に申請する者
の主論文は、博士(後期)課程在学中、又は認定退学後に掲載、又は掲載予定であること。
(4)主論文は、原則として第一著者(筆頭者)であること。
ただし、論文に第一著者と同等の貢献をした旨明記された共著者(順位は問わない)である場合は、
その者の論文とすることができる。なお、その場合、学位申請者(第一著者である場合を含む)が担当し
た 部分を別途レポートにまとめ、学位申請時に参考資料として提出すること。
(5)複数論文を合わせて主論文とする場合で、そのいずれも共著の場合は、少なくとも一編は、申請者が
筆頭者であること。
大阪大学大学院 医学研究科
引用元: https://www.med.osaka-u.ac.jp/education/students/doctor/application1-2-2#info
2025年6月更新
博士学位申請(課程博士)について(通知)
1.学位論文の審査を受けるにあたっては、主論文1編を提出することを要します。
主論文は、和文の場合は単名であること、欧文の場合は共著も認めますが、筆頭者であることを原則
とします。
当該論文がpeer-review journalに掲載された(あるいは掲載予定)論文であること。
(『eLife』は投稿journalとして認めない。※1参照)
なお、当該論文の掲載雑誌が【PubMed、Scopus、Web of Science】のいずれか1つ以上で閲覧可能で
あること。
九州大学 農学研究院 生命機能科学専攻
引用元: https://ag.kyushu-u.ac.jp/graduate_school/regulation/
博士課程学位授与基準
1.課程博士においては令和7年度以降に入学、論文博士においては令和7年度以降に論文を提出した者に適用する基準
生命機能科学専攻
博士論文の審査に当たっては、課程博士では査読付き国際的学術雑誌に筆頭著者として1編以上の業績が必要であることとする。また、論文博士では査読付き学術雑誌に5編以上の業績(筆頭著者として3編以上の業績)が必要であることとする。
明治大学大学院 農学研究科
引用元: https://www.meiji.ac.jp/agri/daigakuin/doctor/index.html
2023年度以降入学者
明治大学大学院農学研究科 博士学位取得のためのガイドライン 課程博士
【博士学位請求の要件】
研究業績
学会誌水準の論文2編以上(うち学位論文に関連し、請求者を筆頭著者とするもの1編以上)
が公表されているか、掲載が受理されていること。
※掲載が受理されている論文については、その証明となるものを添付すること。
東京理科大学大学院 創域理工学研究科 社会基盤工学専攻
引用元: https://www.tus.ac.jp/academics/degree/criteria
博士後期課程(博士課程)の学位論文審査基準 [2025年度入学者適用]
【土木】創域理工学研究科 社会基盤工学専攻
主論文を構成する論文の条件
2 編以上(「掲載決定」を含む)。First Author であることを原則とする。
(1)内 1 編は土木学会論文集またはこれと同等のレフリー付き論文集に掲載の論文
を含むこと。
(2)レフリー付きプロシーディングスも 1 編と数える。
査読論文の4つの共通要件
ここまで見てきて気づきませんか?
そうです。共通点がいくつかあります。
それは、
- 「査定」のある
- 「英文学術雑誌」に
- 「1編以上」
- 「掲載(受理)」されていること
です。
この4項目は思った以上に難しいです。
1. 査定のある
これは「査読がある」や「インパクトファクターがある」と言い換えられたりします。近年問題になっているハゲタカジャーナルを認めない、というのもあります。ただ、明確にハゲタカジャーナルを名指ししている大学はかなり少ないです。
なので、これは研究室の先輩や教員に聞いてみる必要があります。これを疎かにすると、論文はあるのだが、実は査定のある論文と見なされていなくて、論文としてカウントされない、という事態が起きます。
2. 英文学術雑誌
これは和文学術雑誌は認めない、ということです。
しかし、現代ではPubMedで気軽に論文を検索・ダウンロードできますし、電子辞書や論文執筆のための参考書が多数あります。大変かもしれませんが、数ヶ月、数年かければ英語での準備はできると思います。逆に言うと、数日、数週間で用意することは難しいです。
3. 1編以上
これが最大の問題です。これが1編で良いのか、2編必要なのか、それとも3編なのかで学位の難易度は大きく異なります。
私の感触ですが、博士課程の3年間だけで3編の論文を揃えきるのは、よほど優秀な学生でないとかなり難しいです。修士の2年間も含めて合計5年間でギリギリといった具合です。だからと言って、1編で楽だというわけではありません。1編でも十分に地獄です。
4. 掲載(受理)されていること
これは査読者(レビューアー)や編集者(エディター)が要求してきた追加実験(リバイス)をクリアしていて、学術雑誌に掲載されている。もしくは、掲載の内定(受理)をもらっている、ということです。
通常、学位審査には3~4ヶ月かかります。その学位審査の申請時点で掲載されているのか、受理だけでいいのか、で大きく違ってきます。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
論文だけでもこれだけ項目があるのです。
これらの項目を何年もかけて一つずつ乗り越えていくのが博士課程です。確かに大変ですが、それは最高学位である博士号にふさわしい実力を持つためのトレーニングなのです。
最も重要なのは、入学前に「専攻の基準」をしっかり把握し、志望する研究室が不当に厳しい要求をしていないかチェックすることです。
それでも研究室選びには迷ってしまう場合があると思います。そんな時は私が書いた本がAmazonで出版されています↓。そちらもぜひ、読んでみてください。
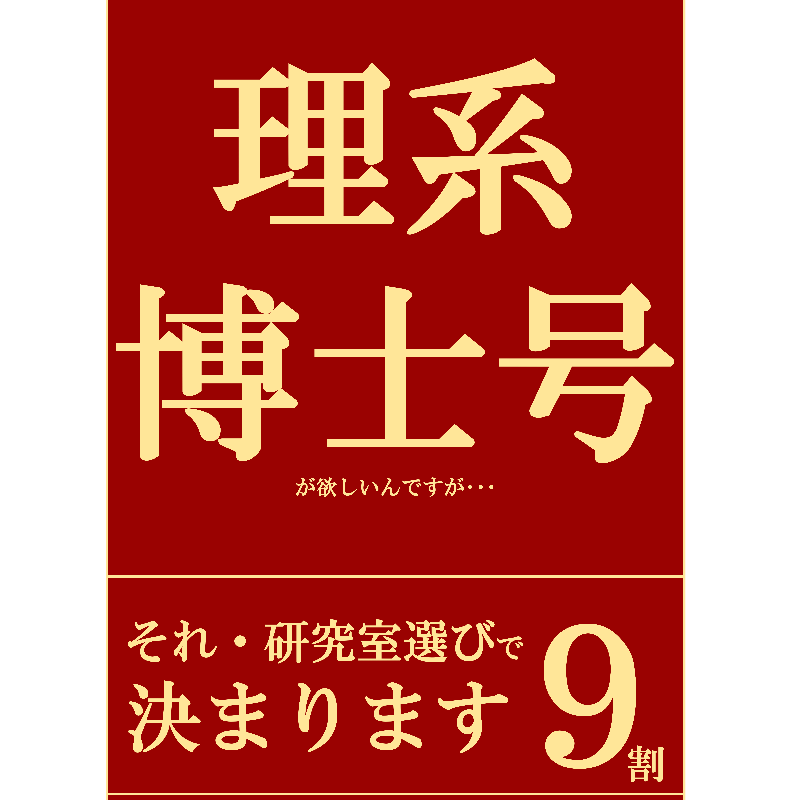
「 理系博士号が欲しいんですが : それ・研究室選びで9割決まります 」
「その研究室、本当に“博士号”が取れますか?」
研究室選びを誤ると、どれだけ努力しても成果は出ない──。
博士進学を目指すすべての理系学生に向けた、実践的かつ現実的な“研究室選び”の決定版!
◆2025年最新版!進化する研究環境に完全対応
コロナ後の研究体制、リモートワーク、科研費制度の変化などを踏まえ、初版から全面改訂。
令和7年度以降の進学希望者に向けた、現代の研究室で「生き残る」ための知識を集約。
◆失敗しない研究室選びのポイントを徹底解説
教授の定年や研究費実績、論文数などの具体的なチェック項目から、ブラックラボ回避のための最新ガイドラインまで、選ぶ前に知っておきたい情報を提供。
◆研究室生活のリアルを完全収録
SNSの活用、異文化協働、心の健康まで。入ってから後悔しないための実践的ノウハウを一冊に。
こんな人におすすめ
・令和7年度の博士課程進学や研究室配属を控える学部生・修士学生
・研究室選びに不安を感じている理系学生
・博士号取得を目指す全ての若手研究者