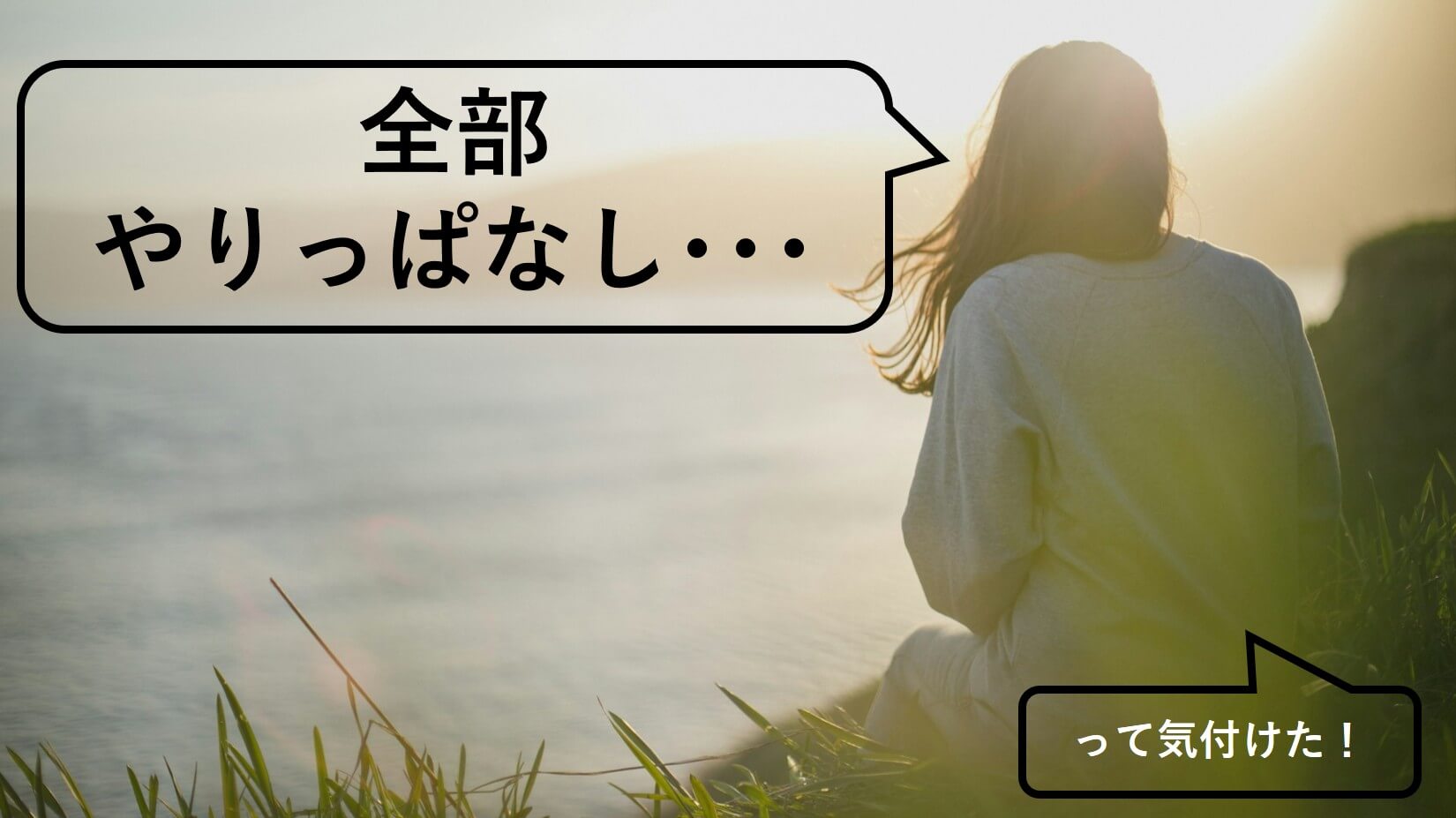介護、育児、闘病などへの支援と補助
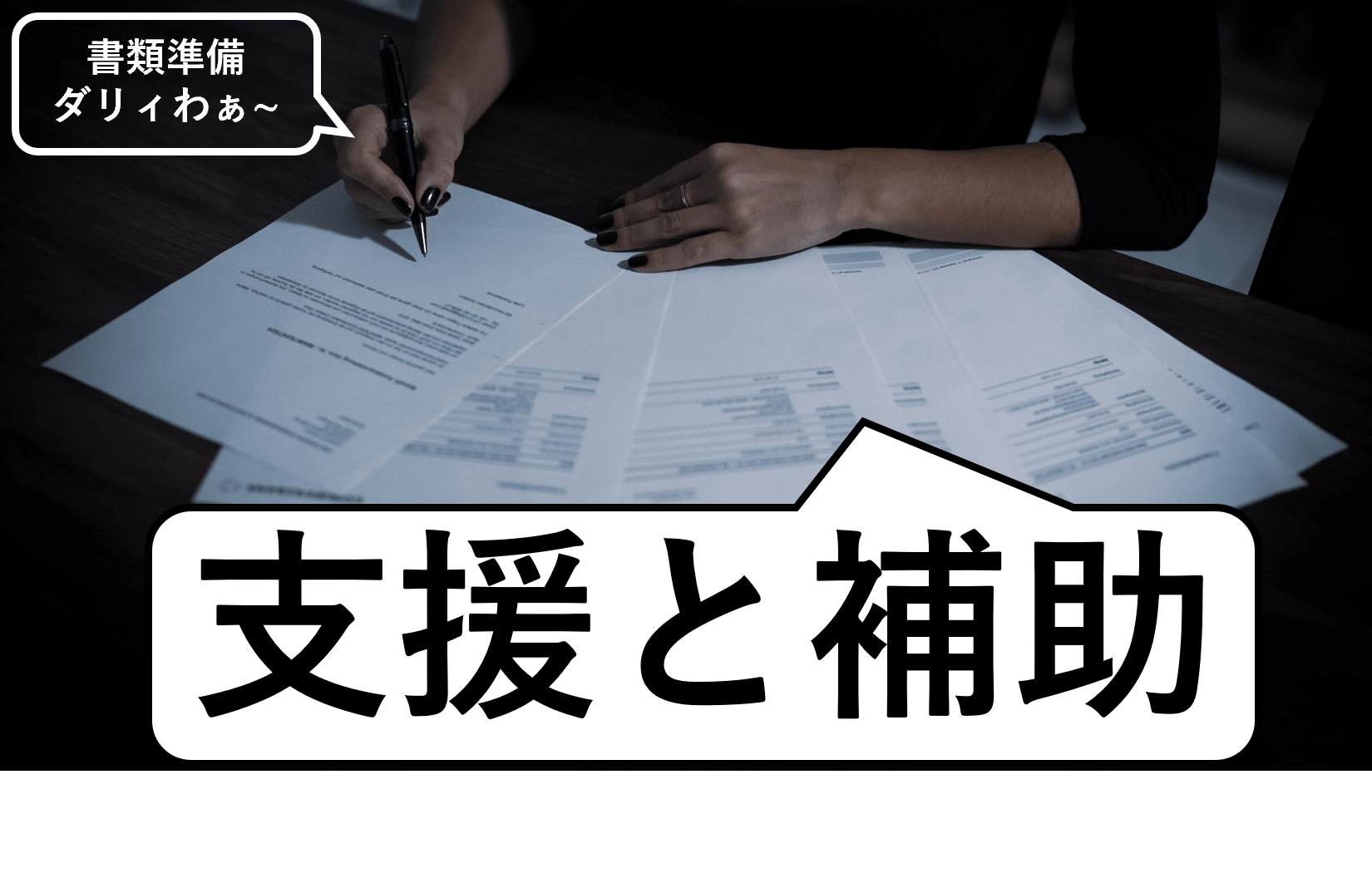
介護や育児、闘病などへの補助の現状
現在の日本では、介護や育児、闘病などで困った状況になった時、何かしらの支援があります。
これはとても素晴らしいことです。昔であれば支援もなく、サービスそのものが存在しないことも多々ありました。
しかし、今回の記事で伝えたいのは、支援の有無や規模は、住んでいる市町村や都道府県、所属している企業によって大きく異なるということです。
そして、たとえ支援があったとしても、すべてを補填してくれるわけではなく、また手続きにも時間がかかったり、多くの書類提出が必要になったりします。
住んでいる街の規模と強さ
「支援の有無や規模が場所によって違う」と聞くと驚く方もいるかもしれません。
ですが、よく考えるとそれも当然のことです。
人口が多く企業も多い大都市では、税収が多く、福利厚生が充実しています。
一方、過疎化が進み、地元産業も小規模で税収の少ない地域では、支援制度が限られていることがあります。
ここでは税収や予算の使い方についての議論はしませんが、**大事なのは「自分が住んでいる地域の制度をきちんと調べておくこと」**です。
どんな支援が受けられるのか、どこに相談できるのかを事前に知っておくと安心です。
就職先の企業の規模と強さ
同じように、所属している企業によっても福利厚生は大きく異なります。
有名な大企業・中小企業・外資系企業・公務員では、補助や休暇制度の内容に大きな差があります。
「うちは大丈夫」と思っていても、実際に調べてみると制度が存在しなかったり、申請の仕方が分かりにくかったりすることがあります。
なぜ申請が難しいのかというと、福利厚生を受けるためには多くの場合、複数の書類を準備し、担当者や上層部の理解を得る必要があるからです。
会社の体制や担当者の経験によって、対応スピードが大きく変わることもあります。
全てが補填されるわけではない
また、支援があるとはいえ、すべてが完全に補填されるわけではありません。
医療保険を例にしても、自己負担がまったくないケースはほとんどありません。
1割や3割といった割合ではなくても、何らかの負担が残る場合があります。
さらに、医療器具などの中には保険適用外のものもあります。
驚かれるかもしれませんが、実際によくある話です。
もちろん、手術などで数百万円の請求がそのまま来ることは稀ですが、数万円〜数十万円の負担が生じることは十分にあり得ます。
手続きが必要
そしてもう一つ大切なのが、支援を受けるには手続きが必要だということです。
企業や公的機関からの支援を受けるためには、市役所や区役所、県庁、府庁、都庁などへ出向く必要があります。
そして忘れないでほしいのは、**多くの支援は「自分から申請しないともらえない」**という点です。
自動的に支援が降りてくることはほとんどありません。
書類の準備や窓口での確認など、慣れていないと手間も時間もかかります。
あらかじめ流れを調べておくだけでも、だいぶスムーズに進められるでしょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
この記事を読んで、「支援って思っていたより大変なんだ」と感じた方も多いかもしれません。
しかし、経験者の方なら「あるある」と共感していただけたと思います。
支援はあるけれど、完璧ではない。
そして、支援を受けるためにはこちら側の準備や手続きが必要になる。
ただ、それを事前に知っておくだけで、心の負担はずっと軽くなります。
困る前に調べておくこと。これが、実際の生活ではとても大切です。
育児や介護などの関連記事があります。そちらもどうぞ↓