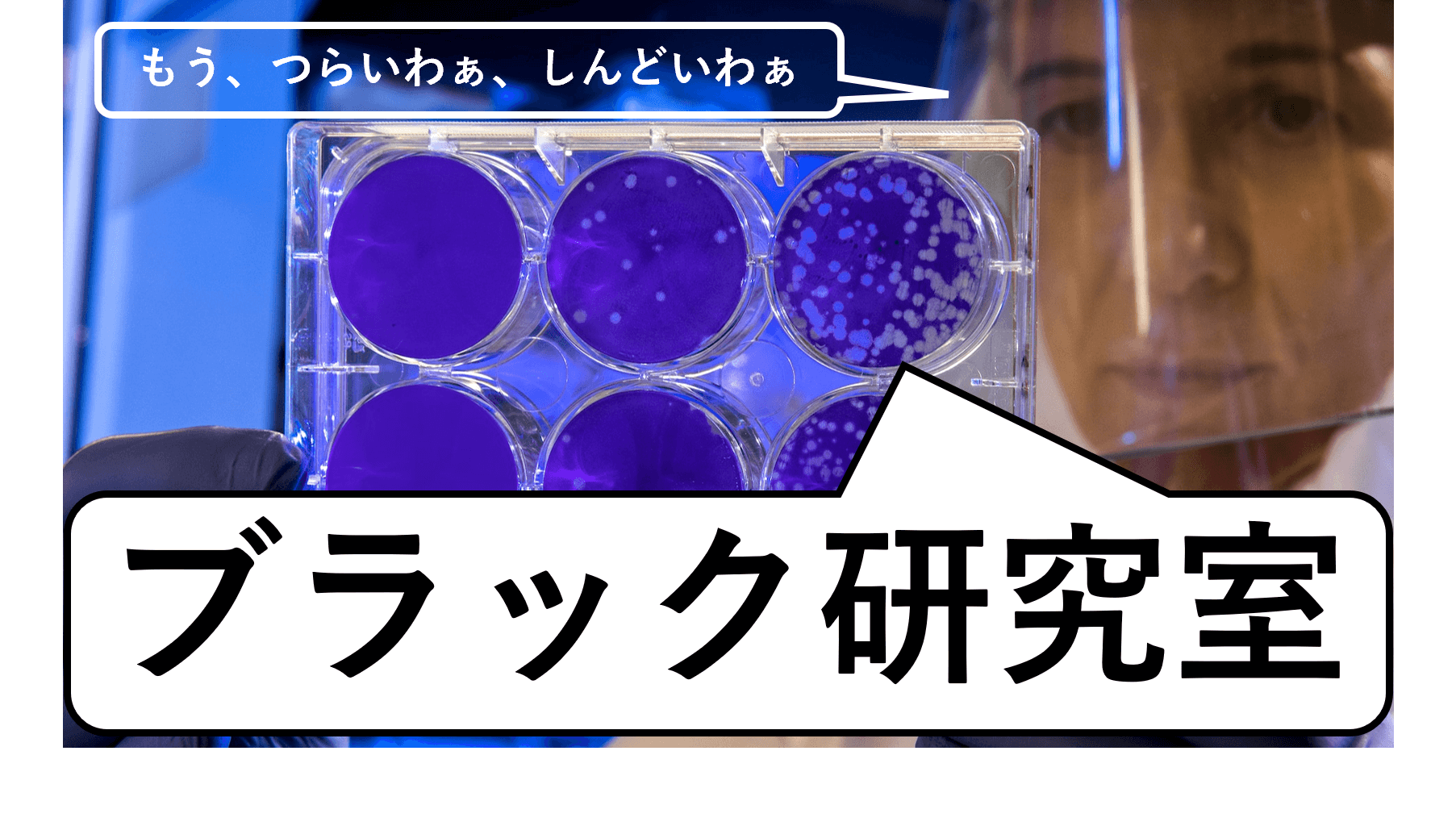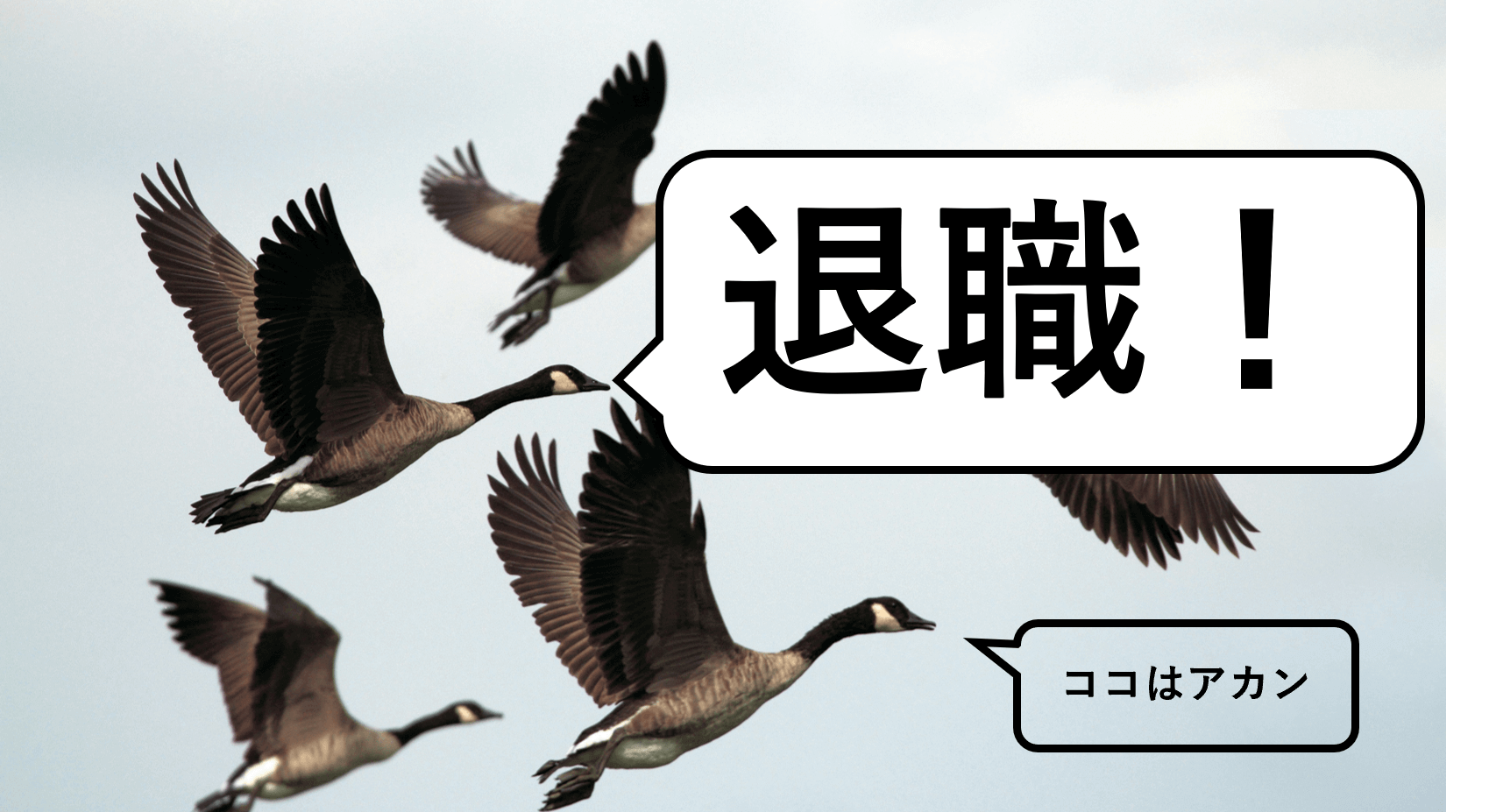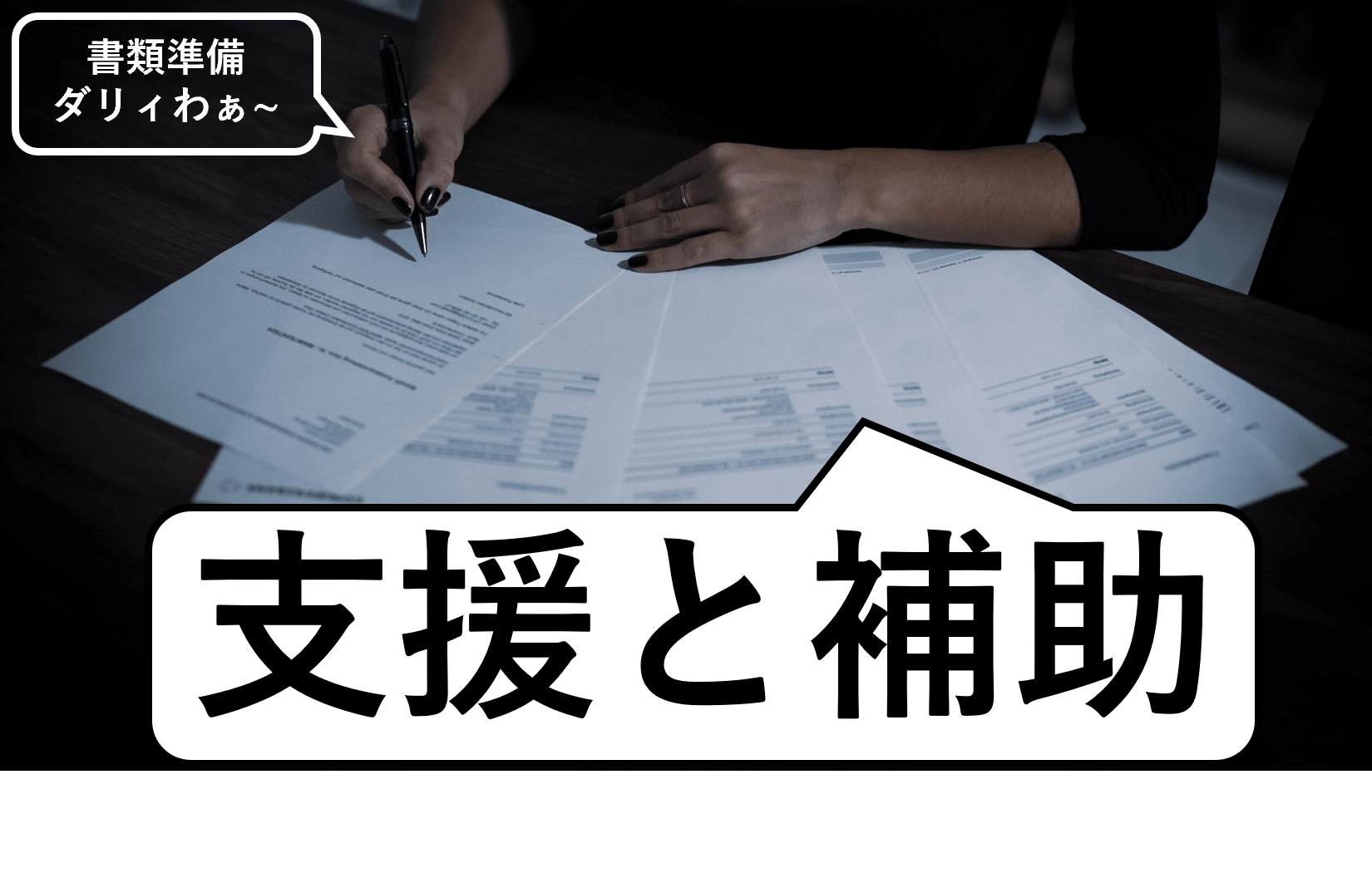介護状態は悪化する傾向がある

第1章 介護状態とは何か
「あなた自身も、いつか必ず介護状態に突入することになる」と、以前の記事で書きました。
今回は、その介護状態に入る原因について少し考えてみたいと思います。
ここでは、みなさんと一緒に「介護状態」について学んでいきます。というのも、私自身、この状態についてまだよく分かっていないからです。先行研究も少なく、体系的に考えられた例もほとんどありません。ですので、ある意味でこの記事は、介護状態を考察する上での世界初の試みになるかもしれません。
第2章 介護状態を構成する二つの要素
介護状態になるには、少なくとも二つの要素が必要だと前回書きました。
一つは「自分自身を含めた周りの存在」。もう一つは「助けを必要とする状態になること」です。
今回はまず、「自分自身を含めた周りの存在」について、もう少し掘り下げてみたいと思います。
一般的に介護の対象となるのは、高齢になった両親です。
しかし、それだけではありません。兄弟姉妹、子ども、親戚、恋人、友人、知人――さらには、小さい頃から一緒に暮らしてきた犬や猫などのペットも含まれるでしょう。
そして、忘れてはいけないのが「自分自身」です。
第3章 「助けを必要とする状態」とは
次に、「助けを必要とする状態になる」について考えてみましょう。
これは単に「高齢になったことで身体が不自由になる」というだけではありません。
病気によって手足が動かなくなる、PTSDなどの精神的要因で身体が動かなくなる、あるいは法律や教義によって行動が制限されるなど、非常に多様な形で現れます。
第4章 複数の介護状態が重なるとき
さらに重要なのは、「自分自身を含めた周りの存在」が「助けを必要とする状態になる」ケースが、いくつ同時に存在するかという点です。
たとえば、70代の人が、90代の寝たきりの母親を介護しているとします。
この場合、「自分」が「高齢で歩行が困難」+「母親」が「高齢で寝たきり」となり、二つの介護状態が重なります。
あるいは、「自分」が「うつ病」+「子ども」が「不登校」という組み合わせも考えられます。
つまり、「介護状態」というのは一つではなく、
「介護状態(自分)」+「介護状態(母親)」=「ダブル介護状態」
というように、複合的な形をとるのです。
第5章 介護状態の進行性
そして、この複数の介護状態には、進行性があるように思えます。
つまり、一つ目の介護状態を抱えているうちに、二つ目、三つ目の介護状態が新たに発生してしまうのです。
たとえば、先ほどの例のように、70代の人が90代の母親を介護していた場合。
やがて本人も高齢であるため、介護疲れからうつ病を発症してしまう――。
こうして、「母親の介護状態」に加えて、「自分自身の介護状態」が重なっていきます。
第6章 「普通」に戻れないという現実
そして何よりおそろしいのは、この介護状態が自然に消えることは、ほとんどないという現実です。
唯一消えるとすれば、それは介護の対象となっている原因そのものが失われた時です。
言い換えれば――亡くなった時、です。
つまり、一度介護状態に突入してしまうと、「普通の生活」に戻ることはほぼ不可能になります。
ここでいう「普通」とは、介護状態を前提としない社会での生活のことです。
今の日本社会では、介護を前提とした設計も、私たち自身の意識的な備えも十分ではありません。
だからこそ、この「介護状態」はおそろしい。
私たちは、あまりにも無防備なのです。
第7章 それでも、備えるという希望
だからこそ、余裕のあるうちから準備をしておくことは大事です。
介護状態は、ある日突然やってきます。
そのときに慌てないためには、「助けを求める力」を日頃から鍛えておく必要があります。
SNSでも、地域の集まりでも、どこでも良いのです。
しんどい時に話せる場所が、聞いてくれる人が――たとえ一人でもいれば、状況はまったく違ってきます。
私自身も、その途中にいます。
完璧ではありませんし、うまくいかないことも多いです。
それでも、「助けを求めること」や「人とつながること」を、少しずつ練習していくことが大切だと感じています。
介護は「誰かを助けること」ではなく、「助け合うこと」。
そのために必要なのは、完璧な知識や体力よりも、つながりを保つ勇気かもしれません。
🪞あとがき
介護状態という言葉を、私たちは“他人事”として聞き流しがちです。
けれど実際には、誰もがそこに向かって歩いています。
この文章が、少しでも「今のうちに考えておこう」というきっかけになれば幸いです。
関連記事があるので、そちらもどうぞ↓